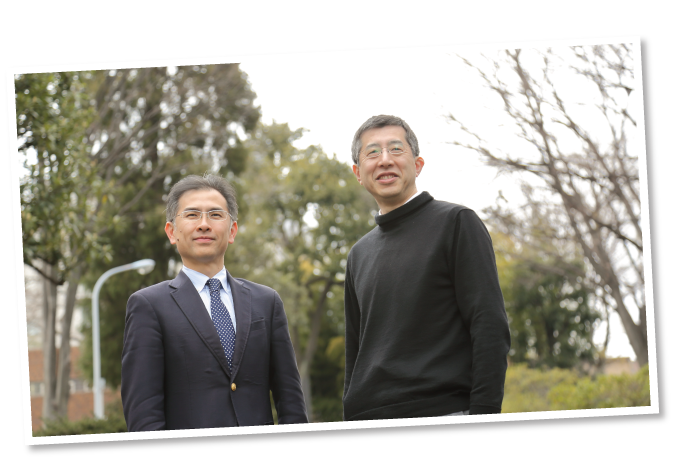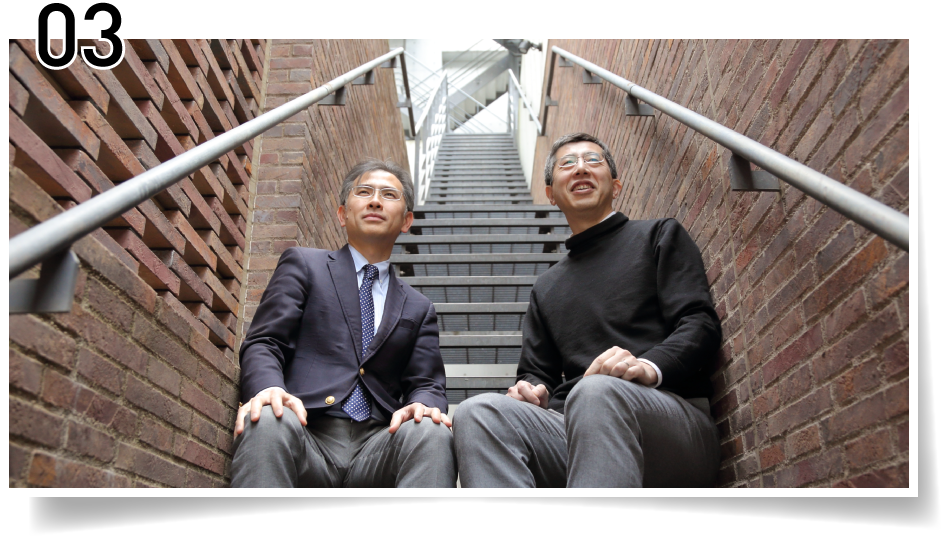
社会を変えるチカラは呼応する。
対話する「未来論」第3回は、身の回りにあるテクノロジーを利用した支援技術開発に取り組む巖淵 守准教授と、レーザー技術を中心に光通信の幅広い融合的応用に取り組むセット ジイヨン准教授。二人はもともと、とても近い分野を専攻しており、現在に連なる研究の起点は、前世紀の終わり、1990年代のイギリスにさかのぼるという──。

巖淵:ええ。1997年に英国ダンディー大学に行ったのですが、実は僕もそれ以前の専門は電気工学だったんです。日本では、博士号を取得するまでその分野の研究を行っていて、仲間にはレーザーを使う人も多かったし、今でもセット先生の分野にはすごく関心があります。ただ僕の場合は、当時阪神・淡路大震災(1995年)があって、自身の価値観が変わったんですね。自分の研究が世に出るのは20、30年先かもしれないと周囲から言われて、それまで僕は待てないと思った。やはり、日常的に相手に会って「ありがとう」って言ったり言われたりする関係を持ちたい。それで当時テクノロジーを利用したコミュニケーション支援の研究では世界の先端を走っていたダンディー大学へ行くことにしたんです。
セット:素晴らしいですね。それを決意して行くというのは。
巖淵: いやいや。当時僕はエレクトロニクスの中でも物性に関わるシミュレーションソフトの開発を手がけていて、そのスキルを伸ばしながら発話が困難な人のコミュニケーションを支援するシステム作りを始めました。それ以来今日まで、支援技術の開発を続けています。
セット:僕はレーザーをいろいろな分野に応用する研究をしています。現在取り組んでいるのは、例えばカーボンナノチューブを用いた短パルスレーザーによる3次元形状計測や、フェムト秒レーザーによる微細材料の非熱加工技術への応用化などです。それから広帯域レーザー光源を使った共同研究として、バイオ分野への応用や、ピコ秒パルスレーザーの多光子蛍光効果により顕微鏡の映像をいっそう鮮明にする研究開発なども行っています。
セット:妻と知り合ったのがイギリスで、彼女が日本人だったからです。1998年から先端研で約2年研究し、その後家族でアメリカへ渡って、ベンチャー企業に入りました。光通信が華やかだった時代ですね。ところが半年でアメリカ同時多発テロ事件が発生して、結局約1年で日本に戻ってきました。先端研ではちょうど第1号のベンチャーが立ち上がっており、迷わず参加したんですが、3年間経っても売れなくて、大赤字になった。
巖淵: 売れなかった一番の理由は、価格ですか?
セット:価格だけでなく、ニーズもなかったですね。要するに先端的過ぎたんです。通信スピードが10ギガの時代だったので、すぐに40、160ギガと発展するだろうと想定して、それに必要なある部品を開発していました。ところが当時テロの影響もあって、スピードをすぐに上げなくてもよくなった。しかも後になって160ギガになった時には、コヒーレント通信が出来ていて、結局永遠に要らなくなった。2005年、会社の赤字は6億円で、創業者の3人が責任を取って辞めるという……そのあと、大株主から電話がかかって来て「あなた、社長をしてくれないか」と。(笑)
巖淵:それは…。(笑)

セット:恐いですよね(笑)。イギリスでもアメリカでも失敗経験はよいことですが、妻に相談すると、日本では一度失敗したら一生終わりだと言う。どうしようかと迷っている時に、ある方に「社長をやるチャンスは一度しかないかもしれない」と言われ、結局引き受けることにしました。もう一度資金を集めて、当時活況だった自動車産業と連携して、生産ライン上の車体をレーザーレーダーで測る3次元計測機の開発に乗り出しました。10GHz高繰返率のパルスレーザーを使って、距離5メートルまで50ミクロンの精度で遠隔形状計測できる品質管理機械でした。
巖淵:現場のライン上で50ミクロンとはすごいですね。
セット:ええ。3年間、毎日ラボにこもって開発に没頭していました。ついに自動車生産工場で検証テストにパスし、さあ導入しようという時に、今度はリーマンショック(2008年)が起きたんです。プロジェクトは打ち切りとなり、僕はまた通信に戻ることにしました。資金を募集したところ、海外の実業家が大部分の株を引き受けてくれました。その社長も技術出身で「技術がよくても、利益が出なければ意味がない。利益率を見ろ」というヒントをくれたんです。それで僕は初めて、財務諸表を見るという社長業に立ち返りました。そこからがんばって、2010年に黒字転換し、それでもまだ6億円の赤字があったので、利益率20%で成長して、会社を安定させました。さあ次は上場だという時になって、なんとその株主が急死したのです。相続者は、上場には反対でした。説得も空しく、結局、手持ちの少数株を大株主に全部買ってもらって代表取締役社長職を辞任しました。それでひと巡りして、また先端研に戻ったんです。久しぶりに学生と話して、これからは教育をしたいと思いました。不思議なご縁です。

セット:「アルテク」には、興味があります。どのように生まれた言葉なんですか?
巖淵:中邑賢龍教授(先端研)による既に
さまざまなバリアを抱える人々にテクノロジーを届けていくためには、新たに製品を作るよりもむしろすでに身の回りにあるものを使おう。使えるものがない時に初めて作ればいい。それからセミナー等を開いて、人々が考えた優れた使い方のアイデアを集めて他の人にも知っていただこう。世の中でまだ誰も気づいていないかもしれないけど、この機械とこの機能を組み合わせたら、あるいはそこに人の助けが加わったら、初めてソリューションになる、といった届け方を考えています。
具体的な開発例として、読み書きに困難がある児童・生徒に役立つ、タブレットやスマホ用のアプリを開発しています。彼らは見えていても読めない、あるいは読むのにとても時間かかるんですが、聞けばすぐに分かる。そこで文章をパシャッっと撮影すると、すぐに読み上げてくれます。日本語と英語に対応しています。
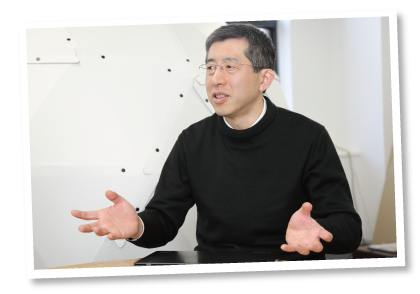
セット:素晴らしいです。
巖淵:小学生に渡して、読み書きに紙と機械のどっちを使ってもいいよって選ばせると、特に読みに困難のある子どもたちは、機械を使い続けます。すると今までテストで例えば15点ぐらいだった子も、その瞬間から90点ぐらい取れるようになる例が生まれるんです。一方、しばらくすると、全体の3分の2の子どもたちは紙に戻ります。日本でもようやく国として電子教科書を提供することが議論されるようになりましたけれども、障害のある子たちにはこのような支援ツールを使える環境が必須だと思いますね。
最近簡単に利用できるようなってきた人工知能のクラウドサービスを使って読み書きの分析を行う研究を始めています。もしかしたらこの子はこういう困難があるかもしれないという推測を試みると、すでに専門家の約7割にあたる精度で診断ができています。ただし目的は診断ではなくて、その先を示すことなんです。つまり、読み書きの困難の傾向があれば、その改善方法を具体的に示せることや、役立つツールをその場で試せる環境を提供することを目指しています。また、困難から解放されると、人はその先に目を向ける、本当にやりたいことを考え始めます。誰だって得意不得意があるのだから、苦手なことは機械や他の人の手を借りて、一人一人の能力が凸凹であっても、ピースで組み合わせたらいい社会を作ることができ、むしろそういう社会の方が強いという考え方です。
セット:なるほど、そういう発想ですね。不得意なことができるようになったからといって、それを仕事にするかといえば、しないですよね。やっぱりみんな、好きなこと、得意なことで勝負したい。
巖淵:ええ。誰しも何かしら困っていることはあって、それをこれからどんどん増えてくるテクノロジーを、身体の一部として使いこなして、自分が、また周りの人も幸せになれることに挑もうよ、と考えています。つまり矯正された能力みたいなものではないか、と最近、中邑先生と話しているところです。例えば、今日、社会制度や眼科医が議論する視力は、眼鏡をかけた矯正視力であって、裸眼視力ではありません。これと同じように、AIが現実化してきた時には、社会にとってAIによって拡張された「矯正知能」こそが議論されるようになると。入試制度も今後大きく変わる必要があるでしょうね。

セット:そうですね。企業等と組むのもいいですね。僕もたぶん誤解していたのですが、障害のある方しか使わないわけではなくて、例えば読み上げタブレットは外国人が日本語を読む支援技術としても使えますよね?
巖淵:はい。ニーズを見出し、的確なソリューションを提案できる人は極めて限られているし、その解決ツールができたところで広まらないのでは意味がない。だから、いろんなメンバーとチームを組んでやるということなのではないかと思います。僕は成果をビジネス的に広げていくことは全く下手だけれど、セット先生みたいな社長業に向いた人とチームになればいいのだと。(笑)
セット:チームを組みましょう。(笑) 先端研は、1998年には電気等の物理系が多い印象でしたけれども、今では医学、バイオ、化学、そして政治等の文系の研究もあるし、バリアフリーも大きな分野になるなど、学際性も豊かですしね。それから、先端研では各研究室が持ち回りでホストする「Happy Hour」という懇親会を、月に1回開催していますね。今どんなことに取り組んでいるのか、分野が離れている先生方や研究員の皆さんと直接話ができて、とても楽しい交流の機会になっていると思います。自由人がいっぱいいる。30年後には、おそらくさらに多分野にわたる研究環境へと進化しているのではないでしょうか。
巖淵:そう、ユニークな人を集めたら面白いということは、みんな直感的に感じていますよね。多様性を認めていることが、先端研の強さではないかと思います。すぐに結果がでなくても自由でいられる反面、全員が任期付きの条件の下で新たな先端を生み出す使命は背負おうと。今後さらにアカデミアの枠も超えて、研究者だけでなく、例えばビジネスでも、あるいは直ちにお金に結びつかない内容でも、他の誰もしていないことの先端を極めた人々も集う中で、「あの人と組もう」が日々起こる、常に変わり続ける組織であり続けて欲しいですね。