
虫を知る、当事者を考える、そして交信する。
学内を車椅子で移動している先生がいる……という出会いをきっかけに、熊谷准教授の当事者研究の講義に参加するようになったという並木特任講師。「先端研の中では一番当事者研究の全体像をシェアしていただいている先生」と、熊谷准教授は言う。その並木特任講師は、「小さい頃から科学者になろうと決めていた」というところから徐々に「虫」の世界へ。「未来論」第6回、エアコンの動作音が響きわたるほどの静かな対話から、それぞれの研究への熱い興味が立ちのぼった。

社会性昆虫と言われるミツバチやシロアリのような虫たちは、みんなで協力して「建築」するなど、インテリジェントな振る舞いを示します……しかし実際には指揮命令系統があるのではなく、1つ1つの個体が他の個体や環境に作用することを通じて、集団全体として一見複雑なプロセスを実現しているんです。これはフランスの昆虫学者のポール・グラーセ(Pierre-Paul Grassé)が最初に提案したことで、彼のこの「スティグマジー(Stigmergy)」という考えは、その後生物学ではほとんど顧みられなかったのですが、このような虫のやり方を参考に、ロボット開発をした人がいます。それが、後にお掃除ロボットで知られるiRobot社を設立したロドニー・ブルックス(Rodney Allen Brooks)博士なんですね。彼は1991年、中央制御装置がなく、足を動かすモジュールや、何かに反応して後退するモーションを起こすといった機能を組み合わせて、ゴキブリみたいな生き物らしい振る舞いをする6本足のロボット「ジンギス(Genghis)」を作りました。人と違う虫たちのやり方は、人間の役に立つ──僕は「虫のおかげです」って言っています。(笑)
熊谷:1個体の中にバラバラな、自律分散的な要素があるんですね?
並木:そのように表現されることも多いですね。神経細胞の塊が人の脳だとすると、虫の場合、分散神経節といって、そのような塊が体の各所にあって、それぞれ独立性が高いんです。スティグマジーの語意は元来、環境に影響を与えて、それに従って行動主体が反応を変えることなんですけども、「環境」の概念に、自分の内部状態の変化、例えば脳の中のシナプスが変わったということも加えれば、すべてスティグマジーだと考えることもできるわけです。

並木:はい。また、神経細胞の数を比べると、人の約800億に対して、虫は10万個という少ない数で対処している。神経細胞をなるべく細くして効果的に配線しようとしても、100ナノメートルより細いとノイズが多くて使えないため、別の戦略が必要になってきます。虫は、まさに生物物理学的な進化のフロンティアでもあるんです。
「自分達にとっては、歩けることよりも、むしろ移動できることのほうが重要なんじゃないか」──そんなふうに当事者が価値づけ、定義しようという機運が高まってきたのは、80年代ぐらいからです。そして2000年代以降、当事者研究が興ってきて、設備や道具といったハードウェアのバリアフリーに加えて、「言葉」「知識」「価値」、という3つのソフトなバリアフリーを、大きな目標にしてきました。例えば私たちが何気なく日常的に使っている言葉が、実は多数派向けにできていることも、徐々に知られるようになったことの1つです。例えば自閉症の人の中には、ちょうど専門用語にも似て、対象となる世界を非常に細かく分節して理解しようとするケースが見られるのですが、その背景には、自分の実際の経験を適切に表現する言葉が素朴な日常言語の中には流通しておらず、ゆえに他人と経験を共有することもできないという事態が横たわっているのです。
 このような考え方は他の分野にも広がっており、例えば統合失調症という精神障害では、かつては幻覚と妄想が消えることが好ましいとされていましたが、昨今では仮に幻覚・妄想が出ていても、本人が社会の中で充実感を持って生活できることが重要だという転換が起こっています。臨床研究をデモクラシー化しようというこのような動きは、世界的に起こっているんですね。これまでは、専門家同士が舞台裏で相談してそのデザインを決めてきた。しかし、当事者にも舞台裏に入ってもらい、臨床の効果を測る物差しの選定プロセスから加わってもらう。さらに、実際的な治療プログラムの開発にも当事者が参加する──というのも、当事者研究というのは研究であると同時に、その実践を通じて当事者自身の回復が達成されるという「セルフヘルプ」をも目指しているんですね。このような実践をプログラム化しようということで、当事者が集まって一緒にマニュアルを作るという研究活動を行いました。
このような考え方は他の分野にも広がっており、例えば統合失調症という精神障害では、かつては幻覚と妄想が消えることが好ましいとされていましたが、昨今では仮に幻覚・妄想が出ていても、本人が社会の中で充実感を持って生活できることが重要だという転換が起こっています。臨床研究をデモクラシー化しようというこのような動きは、世界的に起こっているんですね。これまでは、専門家同士が舞台裏で相談してそのデザインを決めてきた。しかし、当事者にも舞台裏に入ってもらい、臨床の効果を測る物差しの選定プロセスから加わってもらう。さらに、実際的な治療プログラムの開発にも当事者が参加する──というのも、当事者研究というのは研究であると同時に、その実践を通じて当事者自身の回復が達成されるという「セルフヘルプ」をも目指しているんですね。このような実践をプログラム化しようということで、当事者が集まって一緒にマニュアルを作るという研究活動を行いました。
熊谷: また、私は具体的な当事者研究として「痛み」というテーマにも取り組んでいます。実は30歳前後から首が痛くなって、「頚椎症」と診断されました。これをきっかけに、そもそも痛みとは何なのか、というところから当事者研究で明らかにしようとしています。
並木: 虫の場合、痛がっている動作は、実は見られないんです。
熊谷: 痛み行動が表れていない!? 興味深いですね。生理学的にも変化は起きないのですか?
並木: 痛覚のモデルを考える研究はあって、痛みなり侵害なりの情報は伝わっているけれども、痛みとしては表れない。ある程度発達した動物じゃないと痛みはないのかもしれない。
熊谷: 痛み研究の第一人者でアッカリアン(A. V. Apkarian)という方が、痛いイベントが起きてから痛みがピークに到達するまでに、人には平均8秒間のタイムラグがあると発表しているんです。この間にどんな情報処理が行われているのかについては諸説あって、どうやら侵害の大きさと痛みの大きさが単純に比例しているのではなくて、8秒の間に様々な計算をして主観的な痛みを構築しているのではないかと言われています。その8秒間を、どう自分が意識的にコントロールできるのか、と考えると、とてもヒントになります。
並木: つまり、考え方次第で少し体がコントロールできるということですね?
熊谷: ええ。侵害をどう解釈するのか。もしかすると虫は、侵害受容の情報が入ってきても、痛みというものに変換する必要がなかったり、単にしていなかったりするのではないでしょうか。
並木:しかし、情報処理して痛みだと認識することには、なかなか利点がありそうですね?
熊谷: そうなんです。私は、「痛みはメッセージだ」と考えています。もしメッセージとして受け取らず、痛いから「とにかくこの痛みを取ってくれ」と解釈した途端に、せっかくのアラートを見過ごしてしまう。とはいえ、痛みと向き合って意味を探るには、よほど腹を括る必要があります。それから、痛みが運んでくれるメッセージは、通常、身体の内部に原因があると思いがちですけれども、必ずしもそうではない。人間関係がうまくいっていないとか、経済的に困窮しているとかいった困難がある場合にも、人は痛みを強く感じやすい。そういったことをすべて含めて8秒間に計算して、その強度を伝えてくる。
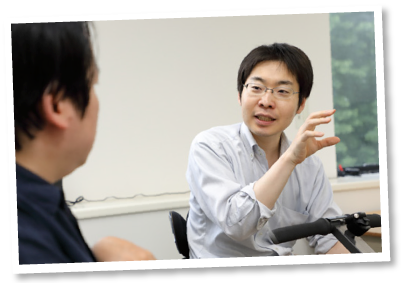
私たちは、日常的に痛みを体験している方々と一緒に、対処マニュアルを作りました。まず痛いと思ったら動いてみましょう。動いた前後で、後のほうが痛みが強くなったら、念のため病院に行きましょう。逆にむしろ気が紛れるようならば、痛みの原因は体の外、あるいは記憶の中にあるかもしれません。次に3つのチェックをしましょう。第1に身体チェック、第2に怒りや不満のチェック、第3に1、2の結果を他人と一緒にチェックしましょう……というように、現場ですぐ使えるようにしてあって、これを元に、様々な現場を回って、痛みを持ついろいろな人たちと一緒に効果検証をしています。
並木: さていよいよ未来についてということですが、私の分野では、ひとつにはクラウドサイエンスのような方向性があると思います。というのも、虫好きの人たちは本当に虫が好きなので、ボランティアとしてみんなで調査を進めていくという伝統がすでにあるんです。例えば渡りの蝶で「アサギマダラ」という大型で美しい紋様を持つ蝶がいるのですが、これまでも各地の虫好きの人たちが、捕まえては放して大陸移動の調査をしてきました。また、地球上の全部の虫を調べようとしたら──おそらく100年かかっても無理でしょうけれども──どんな方法があるのか、という問いも起こってきています。
熊谷: そのようなシチズンシップ・サイエンスと、民主化を目指す当事者研究はどこか共通している部分がありそうですね。これまでユーザーでしかなかった人が、臨床研究を「みんなで作ろうよ」と動き始めている。しかし当事者研究の場合、やはり研究としての方法論の確立が難しい。先端研の様々な専門家の方々との議論を通じて、ヒントが欲しいと思っています。
並木: いやむしろ、去年も当事者研究の講義を聴講して、非常に科学的な方法論だと感じました。仮説を立てるところから始まって、本当に1つ1つ検証していく……。
熊谷: 科学的な方法を手本に進めてはいるのですが、まだまだ多くの人々を除外しているのではないかという感覚はあるんです。例えば仮説の検証段階で使う実験道具は、誰もが使いこなせるわけではなかったり、それを論文化していくプロセスもみんなにとって決して身近なものではなかったり……既存のサイエンスの枠組みは、堅牢な建物のように方法が厳格に整備されているので、いかにしてその裾野を広げて、みんなで作る方法みたいなものを探究していくのか。宿題は山積みという感じですね。
今日、1つ1つの虫は単純な作業をしているんだけれども、それが全体としてすごく大きな仕事を成し遂げているというお話をおうかがいしましたが、そこからも当事者研究が学べることがあるかもしれないと感じています。まだ直感でしかありませんが、もっと柔軟に方法論を考えないといけないのではないかと、改めて思いました。
並木: 科学的な方法のバリアフリーですね。
熊谷: その通りです。30年先の未来を考えると、今まで言ってきたことをとにかく進めなければいけないと同時に、方法自体もバリアフリーにしていく必要があります。当面、まずは日本で根付いた当事者研究を礎にしつつ、世界で起こっている似た方向性を持った取り組みとネットワークを組んでいくことが重要だと考えています。連携から相互に学び合って、方向性を確認し合い、次の段階として「では、それを日本で展開するにはどうしたらいいか」という形で社会実装していく。このような実践にあたって、先端研の分野融合的なフィールドにとても助けられていますね。



